盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
豆知識 Vol.12
相続の承認・放棄が未定の間の遺産管理 ⑴
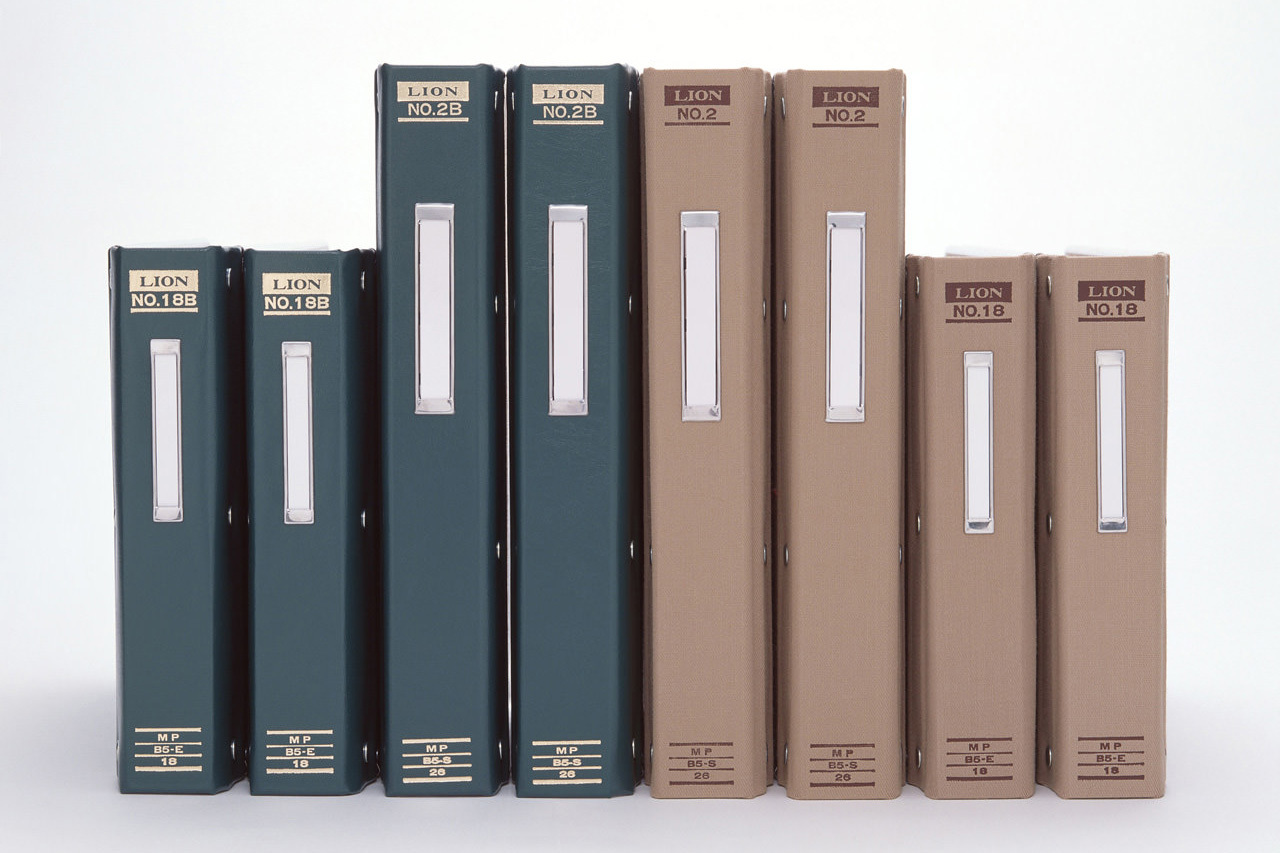
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続について単純若しくは限定承認、または放棄をしなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
そして、相続人は原則として、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、相続人が複数の場合は相続財産は各人の共有に属するとされています。
しかし、その一方で、相続人が相続放棄をした場合は、その者は初めから相続人ではなかったものと扱われます。
このように、相続の承認・放棄が未定の間の相続人は、なんとも落ち着かない立場にあるのです。
それでは、相続の承認・放棄が未定の間の相続人は、遺産をどのように管理したら良いのでしょうか。
管理の方法は、①相続人による管理と②相続財産管理人による管理に分けることができます。
1 相続人が管理する場合
⑴ 注意義務の内容
相続人が管理する場合、法は「自己の固有財産におけるのと同一の注意義務」をもって相続財産を管理しなければならないと定めています。つまり、「自己の財産に対するのと同一の注意」ということです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるという点です。これを法定単純承認といいます。したがって、相続人は、自分がなそうとしている行為が管理行為に止まっているか、処分行為にまで至っていないかを慎重に検討する必要があります。
⑵ 処分行為・管理行為の意義
処分行為とは、財産の現状・性質を変ずる行為をいうとされています。しかし、これだけでは相続財産を売却したり物理的に壊したりすることが処分行為に当たることはイメージできても、これら以外に何が処分行為に当たるのかよくわかりません。そこで実際には、管理行為を超える効果を相続財産に及ぼすものが処分行為に当たると考えると分かりやすいでしょう。
管理行為とは、文字通り「財産を管理する行為」で、①保存行為、②利用行為、③改良行為がこれに含まれると考えられています(⑵に続く)。
2017年9月29日掲載
関連記事
- 相続放棄について(総論)
- 熟慮期間経過後の相続放棄
- 相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合の取扱い
- 相続放棄の撤回の可否
- 相続放棄の無効主張の可否
- 相続の承認・放棄が未定の間の遺産管理⑴
- 相続の承認・放棄が未定の間の遺産管理⑵
- 相続放棄:法定単純承認が問題となる場合
- 相続放棄後の相続財産の管理継続義務
- 相続放棄と相続財産管理人の選任申立て
- 相続資格の重複と相続放棄について
- 親が相続放棄をした場合、子は相続人の地位に立つか
- 相続放棄:熟慮期間の起算点について
- 相続の限定承認について
- 相続放棄と登記(相続放棄と第三者の関係)
- 相続の承認・放棄の期間伸長について
- 相続放棄をした相続人は財産分与を求めることができるか
- 相続開始から3ヶ月経過後に多額の債務の存在が明らかになった場合、相続放棄できるか

