盛岡の弁護士による相続のご相談
佐藤邦彦経営法律事務所
岩手県盛岡市中央通1丁目8番13号 中央ビル2階
豆知識 Vol.69 相続開始から3ヶ月経過後に多額の債務の存在が明らかになった場合、相続放棄できるか
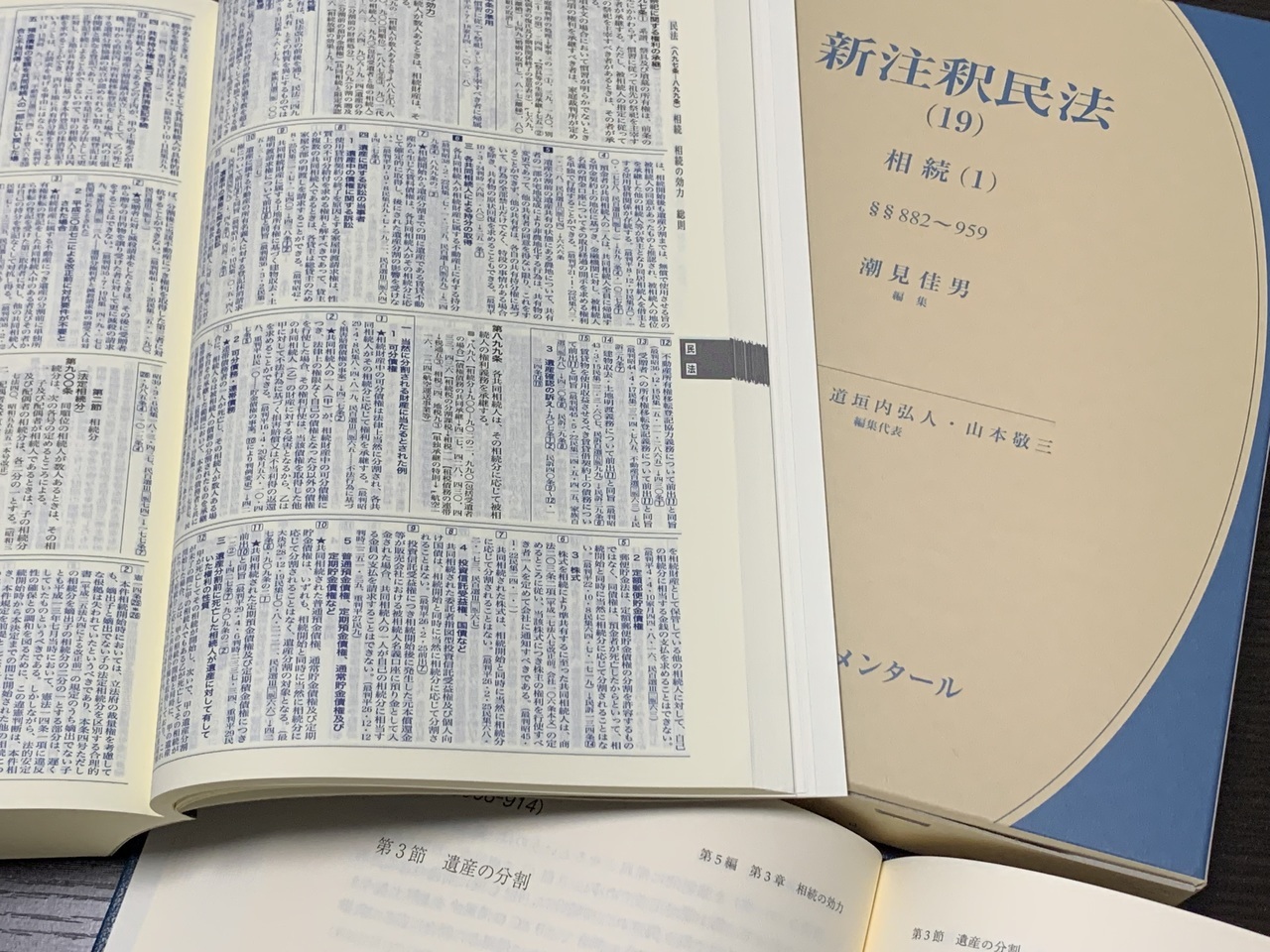
本コーナーの各記事の内容は、特にことわりがない限り掲載時点の法令に基づいたものとなっておりますのでご注意ください。
********
家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、自分のために相続が開始したことを知った時(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内にしなければなりません。
この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間については、どの時点が起算点になるかが問題とされています。
■ 最高裁判所の判断
熟慮期間の起算点について、最高裁判所は「相続放棄のための熟慮期間は、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算すべき」としています(最決平成13年10月30日)。
つまり、言い方を変えれば、相続を承認するか放棄するか検討する契機、きっかけとなるような事情が相続人に生じたときが熟慮期間の起算点になるということです。
■ 事例検討
それでは、相続開始から3ヶ月経過した後に被相続人に多額の債務があることが明らかになった場合、相続人はもはや相続放棄をすることはできないのでしょうか。
1 相続人が被相続人と生前疎遠であり、その財産状況を全く把握していなかった場合
これは例えば、被相続人は東京に住んでいると聞いていたが具体的にどこに住んでいるのか、どんな生活をしているのかは知らなかった、というような場合です。
このような場合は、相続人には検討の契機が与えられていなかったわけですから、多額の債務の存在を知ったときが熟慮期間の起算点になると考えられます。
したがって、債務の存在が明らかになったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができるでしょう。
2 相続人が被相続人に自宅土地建物などがあることを認識していた場合
これに対して、被相続人が自宅土地建物といった積極財産を有していることを相続人が知っていた場合は、相続人には検討の契機が与えられていますので、熟慮期間の起算点は相続開始時点ということになるでしょう。
したがってこのような場合は、相続放棄は難しいと思われます。
■ まとめ
最高裁が示した基準で相続開始から3ヶ月経過した後に相続放棄が認められるのは、実はごく限られた場合なのではないでしょうか。
普段それほど密な付き合いをしてこなかった親類縁者でも、相手が自宅不動産を所有しているのか、それとも借家暮らしをしているのかという程度のことは通常は知っているように思われます。
特に第一順位の相続人(子、代襲相続人としての孫)は要注意です。
「父母は田舎に自宅や水田を持っていたけど、大した評価にはならない。他に大した財産もなかったから、放っておいてもいいかな。」
そういう発想は危険です。
なぜなら、上のような財産であっても「相続すべき積極財産」に当たり、相続人はそれを認識しているといえるからです。
これに対して、自分よりも先順位の相続人がいる方は、先順位相続人が相続放棄をしなければ相続人の地位に立たない訳ですから、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められることは多いでしょう。
2018年6月20日掲載
関連記事
- 相続放棄について(総論)
- 熟慮期間経過後の相続放棄
- 相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合の取扱い
- 相続放棄の撤回の可否
- 相続放棄の無効主張の可否
- 相続の承認・放棄が未定の間の遺産管理⑴
- 相続の承認・放棄が未定の間の遺産管理⑵
- 相続放棄:法定単純承認が問題となる場合
- 相続放棄後の相続財産の管理継続義務
- 相続放棄と相続財産管理人の選任申立て
- 相続資格の重複と相続放棄について
- 親が相続放棄をした場合、子は相続人の地位に立つか
- 相続放棄:熟慮期間の起算点について
- 相続の限定承認について
- 相続放棄と登記(相続放棄と第三者の関係)
- 相続の承認・放棄の期間伸長について
- 相続放棄をした相続人は財産分与を求めることができるか
- 相続開始から3ヶ月経過後に多額の債務の存在が明らかになった場合、相続放棄できるか

